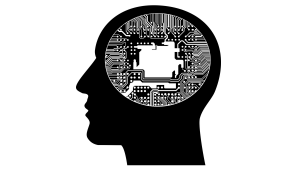2025年度の税制改正が成立し、2025・26年の2年間は、所得税の基礎控除額が納税者の合計所得に応じて変わります。一方、住民税の基礎控除は据え置かれました。改正の大きなポイントは3つあります。
ポイント①:所得税の基礎控除がどの所得層でも合計所得金額に応じて変わる
給与収入(合計所得金額) 改正後の基礎控除額
200万円(132万円)以下 95万円
~475万円(336万円) 88万円
~665万円(489万円) 68万円
~850万円(655万円) 63万円
~2545万円(2350万円) 58万円
基礎控除は2020年から合計所得金額が2400万円以下では一律48万円でした。改正により合計所得金額が132万円以下は恒久的に95万円ですが、132万円超~655万円以下は、今年と来年の2年間のみの適用です。2027年からは132万円超~2350万円以下は一律58万円となります。
ポイント②:パート・アルバイト収入が160万円以下なら所得税がかからない
これまで103万円は「年収の壁」と呼ばれ、それを超えれば所得税がかかっていました。また納税者本人も子の給与収入が所得税の場合150万円以下、住民税の場合160万円以下なら特定扶養控除と同額の所得控除が受けられます。更に配偶者の年収が160万円以下なら所得税で満額38万円の配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。
ポイント③:住民税の基礎控除が変わらない
住民税が課税される最低限の給与年収は110万円と所得税より50万円下回ります。住民税は所得税とほぼ同じ仕組みで、所得控除額は所得税より低額で、税率は一律10%です。例えば、19~22歳の子が160万円まで働けば、所得税はかからず、親は特定親族特別控除を満額受けられますが、子自身は5万円の住民税を負担する事になります。
それでは2024年と比較し、所得税額はどれくらい違ってくるのでしょうか?
【例】年収800万円の会社員(妻・子二人を扶養)の場合(概算)
2024年 2025年
給与収入 800万円 800万円
基礎控除 48万円 63万円
所得税額 24万円 21万円
定額減税 12万円(3万円✖4人) ー
定額減税後の税額 12万円 ー
基礎控除額は増ましたが、定額減税がない為、税負担が増すケースが多くなります。